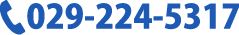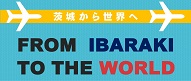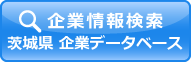ベテル
2022年9月27日
海外への輸出
石村:現在の主な取引先を教えてください。
鈴木:国内の電機メーカー、建材メーカー、医療・歯科・介護機器メーカー様など40社ほどとなっています。そのほか、海外にも納めています。
石村:海外はどちらに納めているのでしょうか。
鈴木:中国、韓国、欧州、米国です。
石村:海外と取引が始まったきっかけは何だったのでしょうか。
鈴木:熱計測事業において「サーモウェーブアナライザー」を物理学会で発表したのですが、その学会に出席していた研究者から声がかかったのが最初です。その研究者は大手企業で材料を研究している部門の人でした。
石村:学会で知り合ったわけですね。
鈴木:はい。そのように当社が直接納めている先のほか、当社が日本のメーカーさんに納めて、そのメーカーさんが中国に持っていくケースも中にはありますね。中国については、現地でフォローアップするのが難しいので、当社が直接輸出する場合は商社が間に入っています。
石村:中国では「サーモウェーブアナライザー」の需要が多いのでしょうか。
鈴木:以前は日本でもグラファイトシートという熱を拡散させる薄膜素材を結構作っていたのですが、今ではそのほとんどが中国に移っています。中国はスマホの素材開発が盛んなんです。
石村:「サーモウェーブアナライザー」の輸出は中国がほとんどなのでしょうか。
鈴木:以前は中国への納品が多かったのですが、最近はアメリカ向けの輸出も増えてきています。
石村:アメリカとの接点は何だったのでしょうか。

医療用プラスチック部品
鈴木:アメリカとは主に学会つながりですね。当社が学会で「サーモウェーブアナライザー」を発表して、その説明を聞いたメーカーや研究者からオーダーが入ってきています。そのほか、アメリカには当社のオーラルヘルスケア事業においても販路を切り開きました。2013年頃からアメリカのカリフォルニア州で開催されている医療向けの展示会に出展し始めたんです。初めのうちは、とりあえず展示会に出て、当社の評価がどんなものか、医療業界の反応を見てみたいという感じだったのですが、実際に展示会に出てみると、医療用は大変厳しい業界であるということが分かりました(苦笑)。まず、医療用のISO規格を持っていないと取引に至ることは難しい。当社としては、それまで長年にわたって大手電機メーカーさんの商品を作ってきていたので、製品の品質管理にはかなり自信を持っていたのですが、医療用は電器部品と違って、ダスト対策や表面のキズがないだけではダメだったんです。医療用は極めてハードルが高いということに気づかされたんです
石村:そのハードルは乗り越えられたのでしょうか。
鈴木:はい。持ち前の開発力で乗り越えました(笑)。
石村:では、医療用のプラスチック部品の輸出先はアメリカが中心なのですね。
鈴木:それが、輸出先はアメリカではなく、ドイツ、フランス、ロシア、韓国が中心となっています。知り合ったきっかけは確かにアメリカの展示会なのですが、顧客はさまざまな地域にわたっています。
石村:アメリカには世界各国から先端品が集まってきますからね。各国メーカーの注目度も高い。さきほど、アメリカでの学会発表の話が出ましたが、御社が直接学会に出席して発表するのですか。
鈴木:はい。自分はアメリカの大学からそのままアメリカの大学院に進んだこともあって、学会でプレゼンテーションするコネクションに恵まれていたんです。
石村:アメリカで学ばれたんですか。それはすごいですね。渡米したのはいつからだったのでしょうか。
鈴木:中学3年の途中からです。父である現会長から、「留学してみたいか」と聞かれて、自分としては海外留学に憧れを持っていたこともあって「留学してみたい」って答えたら、いきなりアメリカのハイスクールに放り込まれてしまったんです(笑)。
石村:それは大変だったでしょう。
鈴木:それはもう大変でしたよ(笑)。最初2~3か月、アメリカの語学学校に通ったあとに、すぐ高校に入学したのですが、回りには友達はいない、日本語をしゃべれる人もいない。そんな中に突然放り込まれたんですから。でも、最初は大変でしたが、次第に馴染んでいきました。大学と大学院では、応用物理を学び、光ファイバーなどの光通信やレーザーを専修しました。
石村:応用物理を選んだのはなぜですか。
鈴木:自分としては、なんとなくだったのですが、父親が理系だったこともあって、理系への道を歩んだんです。その中でも応用物理で光通信やレーザーを選択したのは、将来性があると感じていたからです。父親である現会長の意向を汲んだこともあったのかもしれませんが、いずれは日本に帰国してベテルに戻ってくるつもりでしたから。
石村:なるほど、そこで鈴木社長は、国際感覚を肌で感じて身につけて日本に戻ってこられたのですね。
鈴木:当社は、2008年にアメリカの企業と医療機器を共同開発したのですが、それも留学があってのことだったと思いますので、留学した当初の苦しみも、今では大変ありがたく思っています。
前の記事 一覧へ戻る 次の記事